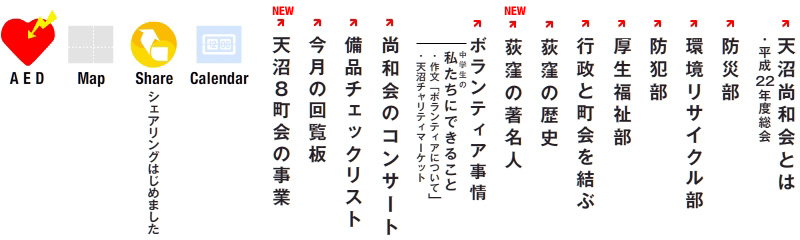荻窪の歴史の夜明け
紀伊半島の熊野那智大社には、江戸一族の資料が現存しております。これは『米良文書』といい、1420年、室町時代にできたものです。ここに「武蔵国江戸の惣領之流」という文書があり、「あさかやとの(阿佐谷殿)」という記述がありま す。荻窪周辺の文献としては、これが一番古いものです。
これが、なぜ那智熊野に残っているかといますと、熊野神社には御師という方がいて、神様を広めるために全国を歩きました。ですからこの文献は、1420年にはこの地に人々が暮らしていたという証拠ですね。うちの熊野神社は、この流れではなく、天沼に朝倉三河守という人が1395年に帰農したことに発しています。現在の、天沼の浅倉さんと、阿佐谷の朝倉さんの御祖先です。紀伊半島から船に乗って逃れてきたと言われています。
杉並の河川ですが、ご存じのとおり杉並には、自然の川は妙正寺川と善福寺川の2本しかありません。そのほかは、玉川上水、神田上水、千川上水とその分水となる千川分水の4つの上水路があります。千川分水は、資料によっては多摩川分水と記述されていますが、私は千川分水のほうが妥当だと思っています。この千川分水は桃園川といわれていますが、この水は、その流れによって水車を回し、穀物などをつく杵を動かすために使われていました。上水を作ったことによって、水車を回すことが非常に大切なことになっていきました。
この上水には、もう一つ重要な意味がありました。自然の川と違い、上水の水の流れをよくするためには掃除が必要でした。しかも、1か所、2か所でやるのではなく、全体を一斉に行わなければなりません。そこで御おふれがき触書が出され、地域の団結によって水路を掃除したため、周り近所、隣村などとの関係ができていったのです。こうした歴史がいちばん残っていましたのは上荻、井草、荻窪村のほうです。井草の方にお聞きしましたら、今でも残っているんだよなんておっしゃっていました。上水は地域の団結がないと維持できないので、人間のつながりも作ってきたわけです。
荻窪の歴史の夜明けは、輸送路としての青梅街道の成立によって始まりました。青梅街道がなければ荻窪もなかったといえると思います。徳川家康が関東に入り、征夷大将軍に任ぜられたとき、将軍の権威を示すために大阪城に劣らない城を造る必要がありました。そのために城の漆喰の主要材料である白い土、これは焼き石灰ですが、これを八王子成木村、今の青梅市から調達した。このために成木街道、今の青梅街道を作ったのです。
青梅街道は甲州街道より2里ほど短かく、荷車や馬の時代ですから、距離が随分違うため、ひんぱんに往来があったということです。青梅街道の整備は、今と違って村の住民がやりました。将軍様の命令で、しかたなく道の整備もしていたというわけです。
土地区画整理の功労者
江戸時代は、中野までが町でした。野方という地名は、字のとおり野の方で、そこから西はすべて武蔵野です。野山があり、雑木林が多かったため、鷹場になっていました。将軍様が鷹をつかってウサギやタヌキを捕るわけですから、そういう獲物が生息しやすい環境を作らなければならない。ですから、自分たちが生活するための畑を増やすとか、家を新しく造ることもできませんでした。
現在のアメリカンエクスプレスのそばにある旧中田村右衛門邸に明治天皇も来られたとありますが、そこは徳川 11代将軍家斉、12代将軍家慶がたびたび訪れた所です。たびたび来られたら大変なんです。鷹場であるということは大変な苦労でした。鷹のために原野の維持が前提ですので、雨水を利用して栽培するムギとかアワ、ヒエなどの灌漑を必要としない、土木工事を行えない農業しかできなかったのです。
畑が自由に作れるようになったのは、明治時代になってからですが、質素倹約が江戸幕府の政策だったため、お百姓さんは非常に質素な暮らしをしていたようです。日常全般にわたって微にいり細に いり統制を受けていました。『慶安の御触書』には「朝起きし農耕に励み、晩は夜なべ仕事に勤み、農具の手入れも怠りなく行え」などと述べられています。その生活が明治になっても、昭和に入って戦争が終わってもしばらく続きました。
大正12年の関東大震災は、死者345万人、第2次世界大戦の戦死者が246万人ですから、その数の多さがわかります。しかし、杉並は火災も、死者もありませんでした。明治22年に新宿〜立川間に開通した甲武鉄道(現在の中央線)で、明治24年に荻窪駅が開設され、大正 11年には、地元の人々に熱心な誘致により西荻駅、阿佐谷駅、高円寺駅が開設されました。こうした背景で、関東大震災以降、東京の中心部から荻窪に引っ越してくる人々が増えていきました。
そんななか、大正 11年に東京都の都市計画区域の設定が行われ、東京駅を中心として10マイル(約16キロ)以内の地域が指定されて土地区画事業が推進されました。高円寺耕地整理組合が大正12年発足、昭和15年に完遂。井荻土地整理事業が大正13年に開始、昭和10年完遂。このあと和田堀、天沼、永福町などで土地区画整理事業が行われましたが、戦争を境にうまくいかなかったところが大半で、杉並の中央部と南部に区画整理できていない地域が残っています。消防署長のお話でも、井草のほうは防災がしやすいが、天沼、高井戸などは消防車が入れないなど防災面でも不安が大きいとのこと。
地域開発の功労者として、内田秀五郎氏の業績が浮かび上がってきます。内田氏は 21年間、村長、町長などを歴任し、人々の生活に道路整備が必要だと考えたわけです。
しかし、道路整備には関係地主の協力が必要です。耕地が減少する、工事費の 負担がかかる、整理工事期間中には土地の売買や宅地使用に制限を受けるなどの理由から、反対する人も多く、なかには石を投げたり、「殺せ」とまで言う人もいたそうです。そのなかで説得を続け、井荻地区の区画整理を成し遂げました。こうした先人の人力のおかげで現在の区画整理ができました。
現在、善福寺公園に内田氏の銅像が建てられています |
 |

青梅街道。

天沼八幡の森近辺での葬式。

荻窪駅近辺。

荻窪駅(昭和11年頃)。

清水町の郵便局(四面道付近)(昭和10年頃)。

荻窪消防署(昭和19年)。

トレーラーバス(昭和25年)

都電(新宿-荻窪間)(昭和25年)。

桃園川(昭和25年)。
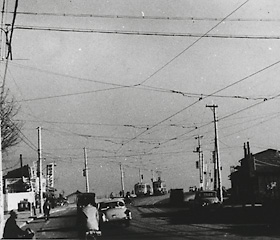
天沼陸橋。

東京オリンピック聖火リレー(昭和39年10月)。
(写真:杉並区広報課提供) |